曹洞宗の聖地として730余年の歴史
金沢駅から南に6㎞。なだらかな野田山の丘陵にあるのが曹洞宗の大乘寺です。 鎌倉時代後期に、加賀の豪族、富樫氏によって現在の野々市市に密教寺院として創建。その後、越前永平寺3世徹通義介(てっつうぎかい)を迎えて、正応2年(1289)に開堂し、加賀国初の曹洞宗の聖地となりました。
藩政期には加賀藩の重臣、本多家の庇護を受け、菩提寺として本多家下屋敷内(現在の本多町)に堂を構えたのち、元禄10年(1697)に加賀藩から現地を与えられて移転。現在に至っています。
禅宗建築らしい七堂伽藍(しちどうがらん)を備えた堂々たるたたずまいで、仏殿は国の重要文化財。他の建物も石川県や金沢市の有形文化財となっています。金沢市内中心部からは距離があり、観光地として喧伝されていませんが、地元では広く知られた寺院です。
境内は自由に散策ができて、総門から山門、庫裏から法堂(はっとう)まで、土間の回廊を歩きながらの拝観が可能です。でも、おすすめは案内付きの拝観(要予約で1名500円、所要時間30分)。建物や仏像についてお坊様の説明を聞きながら見学した方が、理解が深まって楽しいですし、通常は立ち入り不可の建物も見せてもらえることがあります。
また、大乘寺のある野田山の北東斜面は野田山墓地として整備されています。加賀藩前田家初代当主、利家が兄の利久を葬ったことから、前田家一族の墓所となり、明治に入って市民の墓園となりました。墓石の数は5万基余りと伝わる一大霊園地です。高台にある「加賀藩主前田家墓所」は国史跡となっていますが、2024年の能登半島地震の影響で倒壊や破損があるので、見学の際はご注意を。

静寂に包まれる境内


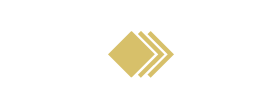

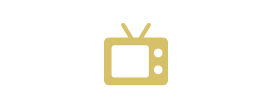

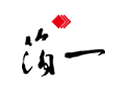




























 観光施設箔巧館
観光施設箔巧館 見る
見る 味わう
味わう 触れる
触れる 買う
買う 箔一について
箔一について 箔一のあゆみ
箔一のあゆみ 金箔の製造工程
金箔の製造工程 金箔の歴史
金箔の歴史